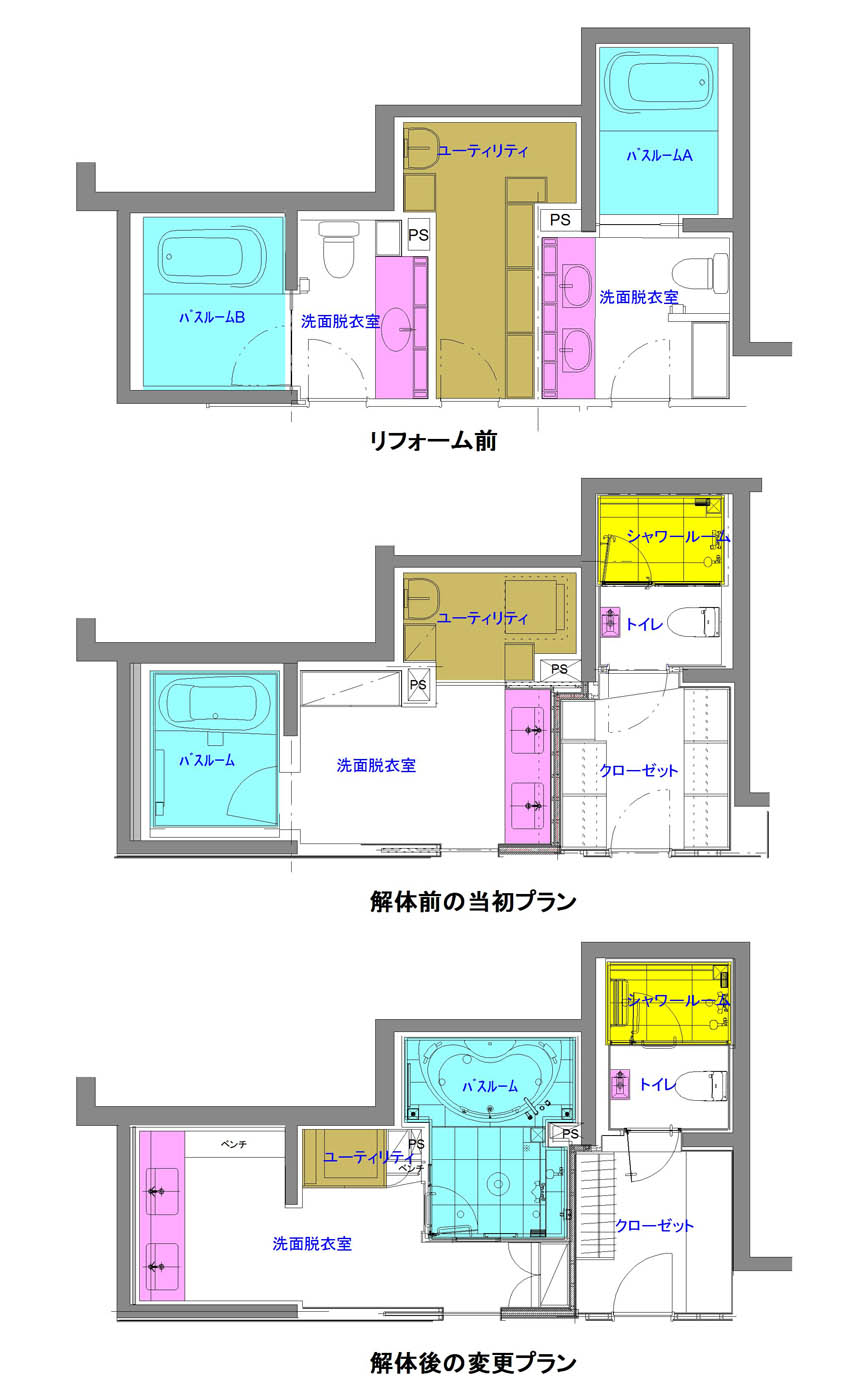解体工事の騒音のことで、リフォーム計画を変更しながらも、工事が進んでいる西麻布N邸プロジェクトで、ダイニングコーナーのテーブル上に吊るペンダント照明選びを進めています。
ある程度、カタログから候補を選んだうえで、担当スタッフの前田君と一緒にショールーム周りをして参りました。まず向かったのが、青山外苑前にあるヤマギワのショールームです。
今回捜しているペンダント照明は、華やかさと非日常感のあるものをとのことですが、カタログでは見えてこないガラスの質感やディテールが重要になってくるので、まずは自分たちの目でそれらを確認してきました。こちらの照明は、きれいではありましたが、照明の下部にはカバーがついており、使ってゆくうちにそこに埃が溜まることが想像できたのと、使っている金物が少々安っぽく感じたので、今回はパスすることになりそうです。
こちらも似たようなデザインですが、秋葉原にあるコイズミのショールームのペンダント照明です。
こちらもアップでディテールをみてみると、ガラスをつっているリングなどの金物が貧弱でした…。
杉並区にあるオーデリックのショールームには、前田君一人で行ってきてもらいました。
お目当てのペンダントライトはこちらでしたが…、
うねったようなガラスのデザインはとてもきれいでしたが、サイズが小さいのと、非日常感という意味では、まだちょっとデザイン性が足りない気がいたしました。
最後のこちらは、日本製ではなくアメリカのアーテリアーズのペンダント照明です。お付き合いのあるベイカー@東京が扱っている照明器具ですが、五反田のショールームには実物がないとのことで、
実物を納品したお店が恵比寿駅近くにあるとのことで、会社帰りに前田君と一杯飲みがてら、こちらのお店に伺って密かに照明器具を撮影してきました。ショールームとは違って、近寄ってディテールを確認することはできませんでしたが、非日常感覚はいっぱいの遊び心があるユニークな照明であることは確認することができました。
西麻布N邸では、ペンダントだけでなく、スタンドやテーブルランプの提案して欲しいとのご依頼を受けておりますので、上記のショールームを回りがてら、幾つかのスタンド型照明も見てきました。こちらはヤマギワにおいてあったフロスのテーブルランプです。
こちらはミノッティのショールームに飾ってあったスタンド照明です。雰囲気もあってとても素敵な照明でした。
こちらはTOYOキッチンが扱っているモーイ(moooi)の置き型照明ボールです。Nさまのお子さまがまだ小さいことと、もう一人お子さまを欲しがっていらっしゃることから、子どもの安全性も考えながら、スタンド照明は検討してゆくことになります。
久々に照明に絞ってのショールーム巡りをいたしましたが、LEDが一般化してからの照明デザインの裾野の広がりを実感することができました。