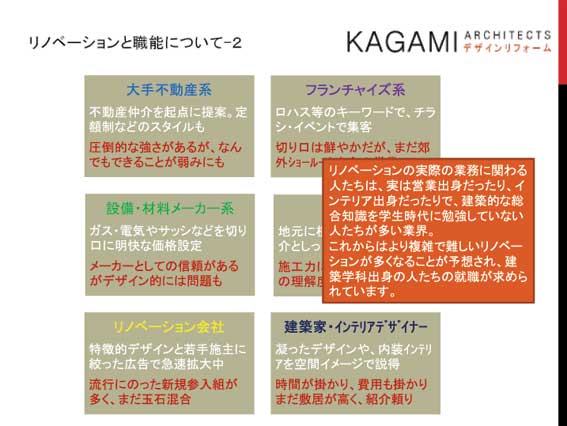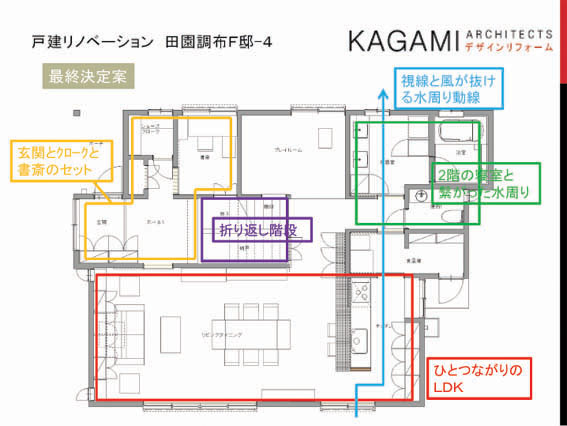こちらも昨年のニュースですが、解体後に墨出しを行った西麻布のマンションリフォームT邸の現場に行って参りました。
いつ行っても、とてもきれいにしている現場です。施工をお願いしているリフォームキューの現場監督坂本さんが、スタッフの竹田さんに天井の高さがどれだけ確保できるかを確認してくれている様子です。
右奥に見えている配管シャフトの状況からどのくらいPSを縮めることができるのか、ギリギリのところを狙って墨出しをして貰っています。
その結果、子供部屋の収納を大きくすることができそうなので、建具を変更すべきか、あるいは建具はそのままで内部の収納寸法を変更すべきかを相談しました。
ベランダに面した壁(背面にガス給湯器があります)の配管は、写真のようにすっかりきれいに整理することができました。
墨出し確認中も、電気工事屋さんや空調屋さんがどんどん工事を進めていました。キッチンのダクトを断熱材を巻きながら施工している様子です。
寝室部分も細かく照明の位置やスイッチの位置も変わるので、電気屋さんが図面を見ながら配線を変えてくれています。