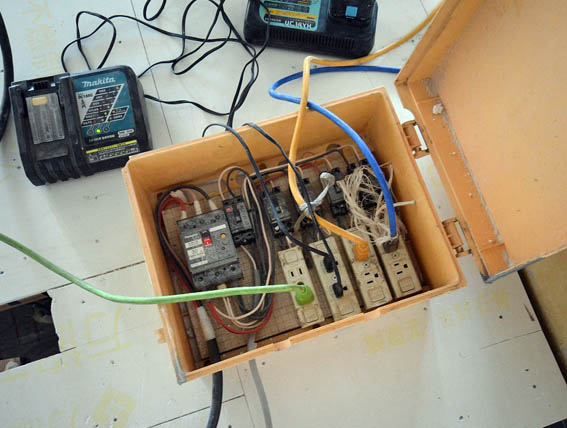青山P邸の現場では、壁と天井が塗装仕上げなので、その下地作りでパテ処理が行われています。
こちらはダイニングの天井のパテ処理状況ですが、中央に黒くスリットが入っているのが照明ボックスです。木製のボックスを天井とフラットになるように埋め込んで、周囲の石膏ボードとの継ぎ目をパテ処理してゆきます。
170平米と広いマンションなので、奥の部屋から順序立ててパテ処理をしているので、こちらリビングダイニングはまだ一度目のパテ処理最中です。最初は、石膏ボードを固定しているビスの頭部分をパテで埋め、ボードの継ぎ目(ジョイント)は寒冷紗を貼ったあとでつぶしてゆきます。
こちらはパテ処理が先行して行われている奥のプライベート廊下と個室部分です。ビスとジョイントを埋めた後、二度目のパテでより幅広く処理範囲を広げている様子が判りますね。
廊下に面した個室の建具周りは、さらにパテ処理が進んで、ほぼ総パテ(全面パテ塗り)状態まで行っています。総パテまでする職人さんは少なくなってきていますが、ここまで進むと、すでに塗装されたような状態に見えてきます。
これはリビングの一角に作っている書庫コーナーの天井ディテールです。目地の個所で、塗装色を塗り分けるので、プラスチック製の目地を入れて貰っています。塗装用パテ処理では、このボードとプラスチックの継ぎ目もパテで一体化させてゆくのです。
これがリビング側からみた書庫コーナーです。ニッチ状に凹んだ箇所に本棚が組み込まれきます。塗装で仕上げるメリットは、天井や壁が一体感を持つことだと思っています。両者がシームレスに繋がることで、空間性を強く感じることができるのですが、その際にどれだけ丁寧にパテ処理したかで、後々ヒビが入ってくる度合いが違ってくるのです。
こちらはまだボード張り後何もされていない玄関ホールです。壁と天井に細いスリットが入っていますが、ガラスの袖壁を嵌め込むC型チャンネルが埋め込まれた状態です。
玄関框と姿見の鏡が貼られる凹みと木製幅木の取り合いディテールです。こういった異種素材が出会った箇所は良い丁寧に考えてゆくことで、空間の一体感が強まると思っています。
こちらは浴室のステンレス枠とタイル張りの枠の取り合いです。白いシールで保護された部分は鏡面仕上げのステンレスで、そこに突きつける形でタイルが貼られる予定です。
塗装下地のパテ処理や、細かいディテールの組立てと目立たない工程が続きますが、この過程をどれだけ丁寧に進めるかで全体の仕上がり感のグレードが決まってくるので、本当に大切なプロセスだと思っています。