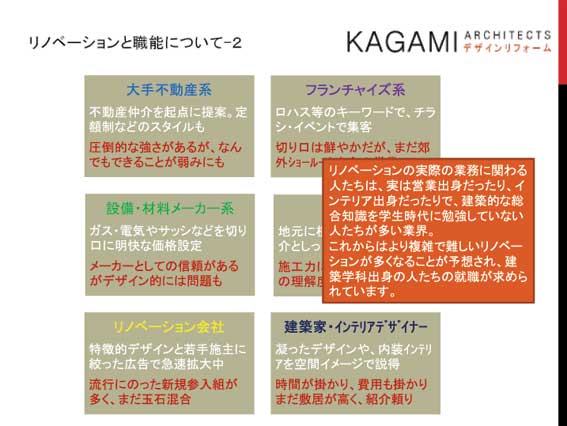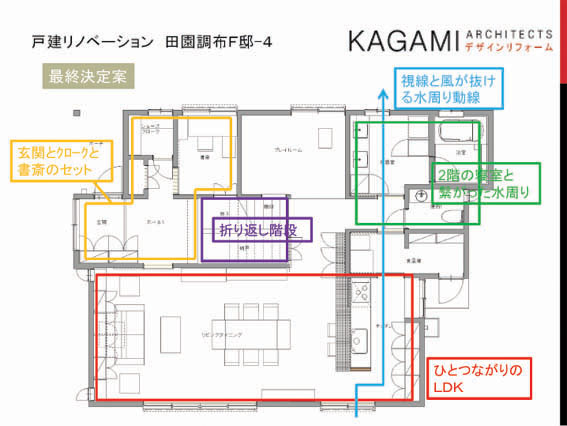東京にお住いのお施主様が、別荘的に使うマンションのリノベーションをお手伝いした神戸M邸プロジェクトは、遠隔地とのことで、施主検査とお引渡しと取説を同日に行うという変則的なスケジュールとなりました。

僕ら設計チームが前日に現地に入り、一通り設計検査をした後でMさまご夫妻に来て頂き、僕らの検査内容をご説明しながら、改めて検査するスタイルとなりました。

こちらは窓側から少し引込んだ位置に設計したリビングコーナーです。左側の白い箱にはトイレと浴室が組み込まれており、左端のカラフルな梯子で上部のミニロフトに上がることができるようになっています。

そのリビングで、施工をお願いした越智工務店の山野社長と担当の金平さん、見積りをしてくれた中村さんがお引渡し書類をMさまご夫妻に説明している様子です。

先ほどの白い箱の後ろ側に周ったシーンです。壁際にキッチンと洗面が一列で並んだ迫力のあるカウンターが続いています。

パネル式の冷蔵庫をご購入頂き、壁と同じポーターズ・ペイントの色で塗装してもらうことで、普段は目に付きやすい白物家電を、背景に溶け込ませるようにしています。

玄関入ってすぐに見えてくる玄関ホールと廊下を仕切る建具は、白金台S邸でも使ったデザインを応用した引き戸としています。

玄関の三和土(タタキ)には、ちょっとクラッシックな雰囲気のある石材・アンティカトラベルティーノをサイズを変えながら張って貰いました。室内に張った幅広のフローリングと、ちょうどフラットにきれいに仕上がっていました。

白い箱の内部に収納されているトイレコーナーです。鏡を独特に使うことで、不思議な奥行き感を演出することができました。

トイレの反対側には、このようなシックなデザインの浴室があります。スペースを無駄使いしないように、収納背部に生まれた空間分をニッチとして取り込んだ箇所には、アクセントとなるように濃い大理石と鏡を張っています。

お嬢様のKちゃんが大好きなピンクでコーディネートした子供部屋で大喜びで遊んでくれました。なかなか伺えない場所だったことと、土日を使っての出張でしたので、2歳になるうちの娘も連れて伺ったところ、3歳のKちゃんと二人で大喜びで遊び、すっかり仲良しになっていました。因みにこちらの可愛らしい家具とインテリアは子供部屋インテリア家具専門店のヴィベルにお願いして作って貰いました。

子供部屋の玄関側にある引き戸には、このようなスライム型(?)をした不思議なのぞき窓を付けています。子供が覗ける高さと、大人が覗ける高さ、そして中間と3つの不思議窓を作りました。

リビングに面したカラフルハシゴにも興味を持ってくれたKちゃん、こちらにも大胆にチャレンジしてくれています。登ることはできても、まだ下りることは危ないので、ママさんに見て貰っています。

写真で説明していても、なかなか全容が見えない神戸M邸ですが、こちらは主寝室から白い箱のカラフルハシゴを見返した様子です。

最後の写真は、このプロジェクトに関連した、お施主様ご家族、不動産屋さんとしてお手伝いしてくれた北野坂商会の玉邑さん、施工の越智工務店の面々と僕ら設計の竹田さんと各務で全員揃っての記念写真です。
改めて素晴らしいプロジェクトのお手伝いをさせて頂く機会を作ってくださったMさまご夫妻、そして遠隔地でなかなか現場に伺えない中で最高の施工パーフォーマンスをしてくださった越智工務店の皆様、そして近隣問題やマンション管理組合への対応に尽力してくださった玉邑さん、どうもありがとうございます!